こんにちは、セツナゲームの管理人「あおむけ」です。
このブログでは「仕事や家庭で忙しい社会人ゲーマーでも楽しめるか?」という視点でゲームレビューをお届けしています。
今回は社会人ではなく、未就学児が楽しめるのかという視点でレビューをお届けします。
というのも管理人の子どもが周りのお友達の影響でポケモンに興味を持ち、「ポケモンのゲームで遊びたい!」と言い始めたのです。
親としては、「未就学児でも一人でできる?」「ゲームは成長に悪影響なのでは?」といった点が心配ですよね。
この記事では、5歳の子どもと一緒にプレイした体験をもとに、未就学児でも楽しめるのか、親がサポートするべき点はどこかを詳しくレビューします。
ポケモンフレンズはどんなゲーム?未就学児でも遊べるの?
5歳の子どもがポケモンに興味を持ち始め、選んだタイトルがSwitch版の「ポケモンフレンズ」でした。
本作はポケモンのキャラクターが登場する知育的なミニゲーム集で、従来のRPGシリーズとは大きく異なる立ち位置の作品です。
制限時間内にシンプルな課題クリアすることで、遊びながら認知力を育てられるのが特徴。
では実際に、未就学児でも問題なく楽しめるのでしょうか?
ポケモンフレンズの良いところ
短時間で区切って遊べる
親として気になるのは「長時間ダラダラ遊ぶことにならないか?」という点。
「ポケモンフレンズ」のメインとなる知育ゲーム部分は80秒×3本のミニゲームで構成されています。

「今日はここまで」と区切りを付けやすく、ゲーム時間をコントロールしやすいのが安心できるポイントです。
我が家では「休日は1時間まで」というルールを設けていますが、その中でもしっかり楽しめています。
1セットのミニゲームでも5分程度で終わるため、1時間もあれば何度か繰り返し遊ぶことができます。
その点で子どもにとっても満足度が高いのかもしれず、終わる時間が来ても「まだやる!」と文句を言うこともありません。
遊びながら認知能力の向上に繋がる
「ポケモンフレンズ」は、ただのキャラクターゲームではなく、以下のような知育的要素があります。
それぞれの課題に工夫があり、自然と観察力・判断力・ルールの理解力を育てられるように設計されています。
実際に子どもがプレイしていると、得意な課題はスイスイ進める一方、不得意な課題では時間切れになることも。
そのたびに「次はもっと上手くやる!」と悔しがりながら再挑戦していました。
親としては、遊びながらチャレンジ精神や集中力が鍛えられるのは非常に嬉しい点です。

親子の会話のきっかけになる
本作ではミニゲームの結果によりイトダマを入手することができ、それを使ってポケモンのぬいぐるみを作ることができます。

遊ぶほどぬいぐるみが増え、「今日は何のポケモンが出るかな?」と子どもが楽しみにしています。
我が家でも「今日は何のぬいぐるみが出た?」という会話が増え、親子のコミュニケーションにもつながりました。

ポケモンフレンズの気になったところ
説明文が漢字表記で未就学児には難しい
ゲーム内の説明は漢字が多く、未就学児が自力で読むのは難しいです。

そのため、最初のうちは親が横でサポートしてあげる必要があります。
一度ルールを覚えてしまえば子どもだけで遊べますが、テキストを読んで進行する部分などは「親子で一緒に楽しむ」ことを前提に考えた方が良いと思います。
とはいえ、子どもは純粋にミニゲーム部分を楽しんでいるので、あまり気にしなくても良いかもしれませんね。
ぬいぐるみの配置操作が少し難しい
獲得したポケモンのぬいぐるみを部屋に配置するモードがありますが、この操作がやや独特で最初はとっつきにくいです。
「置きたい場所に置けない」という不満を子どもが感じることもあり、慣れるまで時間がかかるかもしれません。

ただ、その分「どう置こうかな?」と考える楽しみもあり、思い通りの配置になったときの喜びは大きいようです。
我が家の子どもは「見て、ピカチュウのソファにメタモン置いた!」とご満悦でした。
ぬいぐるみの種類が少なめ
ポケモンといえば1000種類以上存在しますが、「ポケモンフレンズ」で登場するぬいぐるみは有料コンテンツを含めても約150種類。
子どもの「好きなポケモン」が収録されていない可能性もあります。
購入前に公式サイトや攻略サイトをチェックしておくと安心です。
総評
良かった点◎
気になった点△
まとめ
「ポケモンフレンズ」は親の補助があれば未就学児でも十分に楽しめるSwitch向け子ども用ゲームです。
漢字による説明やセリフの読解は未就学児には難しいため、最初は親子で一緒に遊ぶのがおすすめですが、「初めてのゲームに何を選べばいい?」と迷っている家庭にとって、「ポケモンフレンズ」は安心して与えられるタイトルだと感じました。
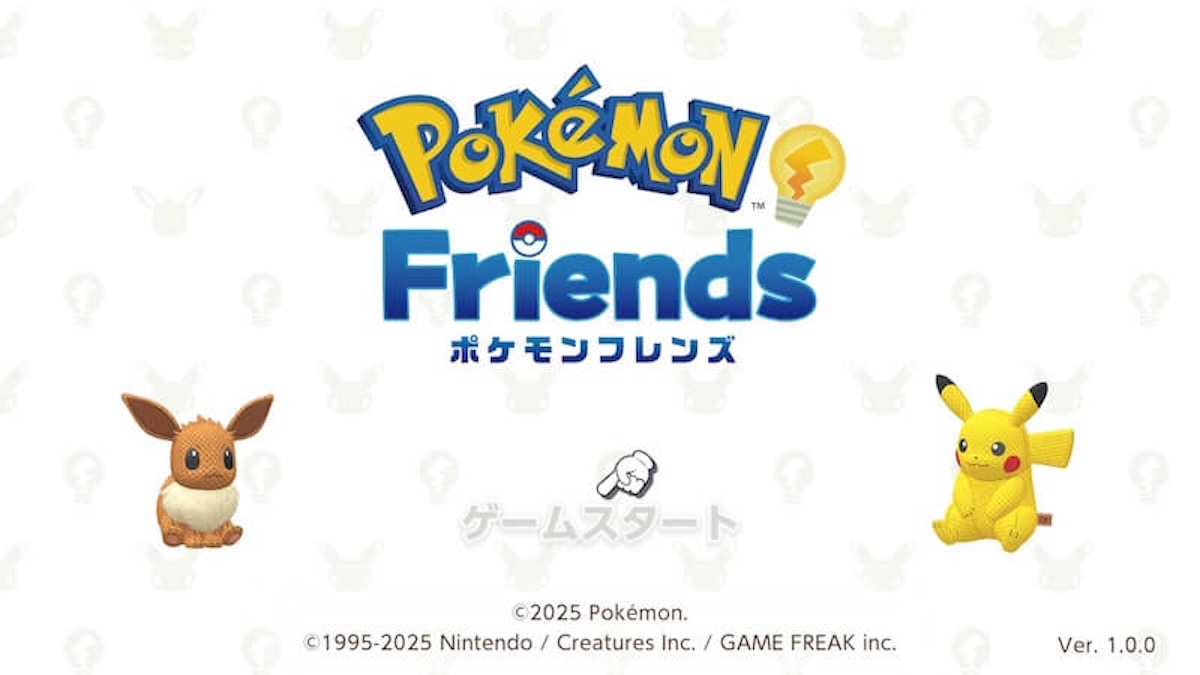
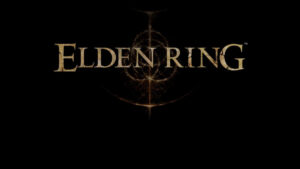


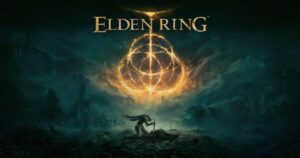
コメント